contents
2025年4月 (1)
2025年3月22日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「『器』からはじめるラーメン×デザイン考」を開催しました。本展のディレクターを務める、グラフィックデザイナーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT館長)と学芸プロデューサーの橋本麻里が、対談形式で、本展開催に至るまでの経緯や展覧会の構成について語りました。
 左から、佐藤、橋本。
左から、佐藤、橋本。
本展のきっかけは、今から13年前の2012年に遡ると佐藤は振り返ります。美濃焼の産地である岐阜県東濃地方の人々が、美濃焼の魅力をどのように世の中に伝えたらよいか、佐藤のもとに相談にやってきたのです。
美濃焼は、織部や志野、瀬戸黒といった桃山時代から続く伝統的な技法を有し、工芸から、マスプロダクト、タイル、工業用ニューセラミックスの分野など、ありとあらゆるものに展開しています。その広がりがあまりにも多様であるため、特徴や魅力をうまく発信できないことに地元の人々は頭を悩ませていました。
佐藤はこの話を受け、それまで専門的に学ぶ機会のなかった「やきもの」の世界を勉強できるよいきっかけになると考え、引き受けることを決めました。
美濃焼の産地に実際に足を運ぶと、歴史的背景もあり分業化されている現場の様子を目の当たりにし、その壮大さに圧倒されたといいます。このプロジェクトを進めるためには中心となる人物が他に必要だと考え、日本美術に造詣の深い橋本に声をかけたことで、両名のタッグが組まれることとなったのです。
現地に何度も通う中で、ある日佐藤は美濃焼の魅力を伝えるものとして「本」をつくることを思いつきます。その本の導入を何にするか議論していたときに、日本のラーメン丼の約9割が美濃焼であることを知り、「ラーメン」を切り口に本を編集するアイデアが生まれました。誰もが食べたことがあるであろう身近な存在、「ラーメン」を入り口とすることで、やきものに特別興味のない人にも美濃焼の魅力を伝えることができると考えました。
残念ながら、本の制作はその後しばらく眠ることとなりますが、美濃焼に関するプロジェクトは「ラーメン」という新たなキーワードを得て続いていきます。
2014年、佐藤もメンバーとして所属する日本デザインコミッティーが運営する、松屋銀座7階・デザインギャラリー1953にて、「美濃のラーメンどんぶり展」を開催する運びとなります。この展覧会は、さまざまなクリエイターらによるオリジナルのラーメン丼とレンゲ25組を並べて展示するという企画で、小規模ながらも開催され、大きな話題を呼びました。
その後、橋本の繋がりで2022年、外務省が世界3都市(サンパウロ、ロサンゼルス、ロンドン)に設置した対外発信拠点の内、JAPAN HOUSE LOS ANGELESとJAPAN HOUSE SÃO PAULOの二箇所にて「The Art of the Ramen Bowl」と題した展覧会を開催。2014年の展示よりはるかに広いスペースでの開催につき、内容も拡充しました。ラーメン文化を紹介するパートや、ラーメンと丼を要素に解剖するパート、美濃焼の伝統的な技法や多様なデザインを紹介するパートなどを追加し、「ラーメン」を入り口に美濃焼の文化を広く発信しました。
2024年には、「国際陶磁器フェスティバル美濃」に関連して、多治見市に所在する岐阜県現代陶芸美術館にて「美濃のラーメンどんぶり展 The Art of RAMEN Bowl」を開催。そして今年、21_21 DESIGN SIGHTにて「ラーメンどんぶり展」が始まり、2012年以来の東京凱旋を果たしました。
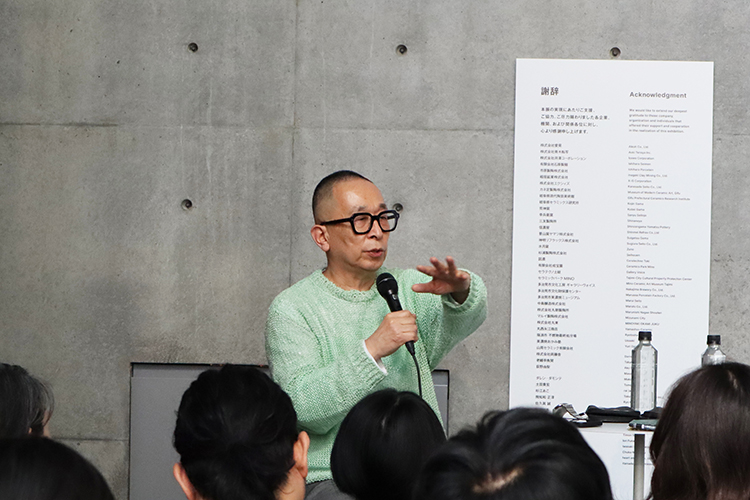
話題は、本展の展示内容の解説に移ります。
展覧会の導入部分である地下ロビーでは、年表やグラフといったデータ、あるいはポップカルチャーと呼ばれる漫画の中でラーメンがどのように描かれてきたかを読み解きながら、ラーメンの歴史と現在について考えていきます。ラーメン店の環境を「音」で感じるインスタレーション作品も体験することで、鑑賞者は「ラーメン」の解像度を上げてからその先の展示へと進みます。
ギャラリー1からギャラリー2にかけては、佐藤による、「デザインの解剖」の手法で迫る「ラーメンと丼の解剖」のパートや、ラーメン丼コレクター加賀保行による約250点の「ラーメンどんぶりコレクション」、2014年から続くアーティストらがラーメン丼をデザインする「アーティストラーメンどんぶり」に新作10組を加えた全40組が展示されています。また建築家・デザイナー3組の設計による新しいラーメン屋台も大きな見どころとなっており、佐藤・橋本の両名もこの「屋台」という存在について、畳んで移動ができるという側面が考えてみるとかなり近未来的であることや、仮設の建築物として、屋台には幾重にも可能性や面白さがあることを熱心に語りました。
そしてギャラリー2の奥のパートでは、やきもののものづくりの根源である「土」に着目した展示空間が広がります。「土をデザインする」技術によって生まれた幅広い製品の数々を一望できるようにしたことで、本展の着地点として、美濃焼の多様さを鑑賞者に示しています。
また、縄文土器が今でも遺跡からそのままの形で発掘されるように、一度高温で焼いたものは再び土には戻らないという事実から、人工物に対する責任、やきものの未来を考えるコーナーも展示。やきものを物理的に砂のレベルにまで細かく砕いた「セルベン」と呼ばれるものを粘土に混ぜ込むことで、またやきものづくりの輪の中に戻す仕組みを紹介しています。

トークの聴講者から、伝統工芸品の存続に関する話題や、佐藤が携わったラーメン店「銀座八五」に関する質問を投げかけられ、対話を楽しんだ両名。最後に、本展に展示されている中から「買うならこれだ」というラーメン丼はあるかと問われます。
橋本は、一つ選ぶのはなかなか難しいと伝えながらも、佐藤の名前を挙げました。佐藤は、自身のラーメン丼をデザインするにあたって考えたこととして、参加するさまざまなクリエイターらはきっと思いもよらないデザインのラーメン丼をつくりあげるだろうと想像したため、自分はいかにもラーメン丼らしいものをつくろうと考えたということ。少しアレンジは入れながらも、意識的に保守的なデザインにしたことなどを説明します。
また佐藤のお気に入りは、竹中直人のラーメン丼。本展のための新作の一つですが、「いい意味で破茶滅茶なデザインで、見た時に仰天した」と感想を述べました。
トークの締めくくりとして佐藤は、冒頭で話題に挙がった「本」が実は10年越しに絶賛制作中であることも紹介しました。
本展に至るまでの道のりや、展示内容、見どころについて、10年以上美濃焼に関するプロジェクトに携わってきた展覧会ディレクターの両名の口から直接語られる貴重な機会となりました。
