contents
竹村真一 (6)
2014年4月13日、ネイチャーフォトグラファーの内山りゅう、新潟大学農学部准教授の吉川夏樹、本展ディレクターの竹村真一によるトーク「田んぼの未来」を開催しました。

はじめに、淡水の水中写真家として、また田んぼ博士として知られる内山が、生物多様性について語りました。もともと魚の研究をしていたという内山は、生き物好きが高じて写真家になったといいます。九州から北海道まで田んぼをつぶさに観察するなかで、田んぼごとに生き物が違うことに注目した内山は、自身の豊富な写真作品を見せながら、単純にに見えて奥が深い、田んぼの世界について解説しました。水陸両方の生き物が棲んでいる田んぼは、まさに生き物の宝庫。多様な生物が棲む田んぼのコメは安全であると、熱く語りました。

続いて、水田をいかに使いやすくするかという農業土木の分野で研究を続ける吉川が、新たな治水の方法として注目されている「田んぼダム」の可能性について語りました。雨の多い国、日本は、その山がちな地形と相まって、世界的に見ても洪水の多い国だといいます。農業土木の歴史は、洪水との戦い、つまり治水の技術の発展の歴史でもありました。中世、近代、そして現代と、治水の思想の歴史的変化をふまえながら、田んぼの仕組みを利用して、降った雨をゆっくりと下流へ流していく「田んぼダム」のコンセプトを披露しました。

二人のレクチャーの後、竹村は、会場に集合していたコメ展参加作家を紹介。最後に竹村とともに本展ディレクターを務めた佐藤 卓もコメントし、本展をきっかけに田んぼとコメ文化の未来について考え続けていきたいと、トークを締めくくりました。
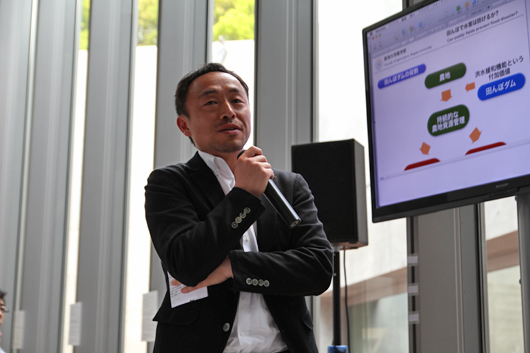




2014年3月8日、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓、竹村真一によるオープニングトーク「まったくのいきもの、まったくの精巧な機械」を開催しました。

2007年に二人が恊働して企画した展覧会「water」を始まりとして、様々なリサーチ、意見交換を経て開催に至った「コメ」をテーマにした展覧会。
まず「既知の未知化」という言葉とともに、水からコメへ発展してきたこれまでの経緯が語られました。「water」開催前に、竹村が佐藤に語った「牛丼一杯に2,000リットルの水が使用されている」という事実。普段の生活において、いかに当たり前に捉えられているものが知らないことに満ちているということを、今回はコメをテーマに、デザインを通して表すことを試みたと両者は述べました。
さらに竹村は「日本食が世界遺産となる一方で、一汁三菜の日本の食文化が消えつつある。日本食は無形文化遺産にあたり、これが"人々の中に生きている"ことに基づくことを考えると、やはりもう一度見つめ直す、リ・デザインの必要性があるのでは」と続きました。
また、様々な分野によって社会が成り立つ現代において、竹村は「様々な分野を扇の要として総合値とするものが必要。それをデザインが担えるのではないか」と語りました。

そして展覧会の作品紹介にトークは進行。「コメ展」はコメづくりの現場と繋がっていること、コメの多様性にもう一度目を向けることを重点とし、千葉県成田市「おかげさま農場」にて企画チームが、手作業による苗づくりから収穫に至るまで体験したことや、全国のコメづくりに携わる方々と恊働によって、多くの作品が制作された模様が紹介されました。今回のトークは、コメの再発見にむけ、企画チームの辿った旅路が語られる貴重な機会となりました。
2月28日(金)、いよいよ企画展「コメ展」が開幕します。
コメは、私たちの暮らしにとても身近で、日々の生活に欠かせないものです。日本では、コメを中心とした食文化を深めつつ、稲作の歴史とともに様々な文化が発展してきました。
本展では、私たちの文化の根幹をなすコメのありようを新鮮な目で見つめ直していきます。そして、その未来像を来場者の皆様とともに考えていきます。
佐藤 卓、竹村真一ディレクションによる「コメ展」に、ぜひご来場ください。





撮影:淺川 敏
2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。
展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。












2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。
展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。








撮影:安川啓太
2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。
展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

左より、佐藤 卓、宮崎光弘、竹村真一 右より、奥村文絵、高柳 功



